CONNECT / 110225 shotahirama
Anarktyp [6' 49" ]
byENG
[1]Ritornell~Line期のMengeシリーズはすべてコレクトしていたかも。この頃のチェチェンズはラップトップにサウンドデバイスを移行していて当時の僕の耳には最もコンフォートな音響作品ばかり発表していました、相当聴き込んでましたね。
[2]Electronic Music Of Theatre And Public ActivityでNew World Recordsから2005年リリースの編集盤。64年頃のlovely系統の音源から80年代のものまで。ムンマ入門編的一枚。
[3]Rainforest / 4 Mographs, 2 Sections From Gestures IIでこれもNew World Recordsからの一枚、もちろんムンマも参戦。
[4]I Am Sitting In A Roomは何度も公言しているマイフェイヴァリットディスク、81年のオリジナルはlovelyからで、なんというか”椅子に座る”事で音楽をセットアップさせて所謂やったもん勝ち作品。ケージの何分何秒だかの作品と同じベクトルじゃねーかとケージに思い入れがない僕はそう思う。Music On A Long Thin Wireも部屋中のワイヤーが蠢いては呻き合う線上になった振動体の固有振動数に対して時間軸すら共振してしまう音響作品。補足だがワイヤードローンはゼロ年代に入りエリック・ラ・カサがエレベーターのワイヤーで、12K宗派のLine教教祖のシャルティエによるlevelsでもエレベーターワイヤーを使用するなど今の時代のサウンドアートへと継続されるコンセプトに。つまりルシエはその先祖。
[5]Pogusからの97年発表のリイシューCD、オリジナルは89年かな、Death of the Moon and other early works.
[6]アメリカ、ロスのサウンドアーティストで彼の代名詞とも言えるスカルプチャーサウンドが当時のスライスドローン界隈でも一際目立ってアートへのベクトルを強く感じる事が出来た作家。ギュンターやブランドンラベルとも活動していてIn Between Noiseは彼の別名義でもあります。99年フランスのSonorisからリリースされたThe Radioは一番最初に買った彼の作品。
レディメイドの乱用と変容 グロテスクな幻想を背後に病的もしくは性的な具音が持続、反復、コラージュといった運動により形成されていく音楽
[photo collage by shotahirama]
![]()
- ENGの活動をはじめるきっかけとなった原体験、また平間さんをビザール作品へと向かわせた初期衝動はいったいどこにあるでしょうか?
そもそもENG、当初は小文字でelectronoise groupと小文字での全表記だったのですが、活動を開始した当初はビザールでもなんでもなく根本的な活動理念はすべて「即興」というタームに置かれていました。ベクトルはすべてインプロにあり。インプロヴァイズドされる集団音響、コントロールフリークを除外した秩序の無い集団即興、不特定多数による初期衝動性の強いアクショニズム、音の本質は表現行為のみにすべてがあると思っていました。ライブを儀式化して、演奏する事のみに重点を置いては崇めて自分たちを煽って、半ば率先してイベントにもライブハウスにも出演していました。
単純にライブする事が好きだったんですかね。結果的な音がなんであれ、それこそがエレクトロノイズグループだ音楽だ即興だ、あわよくばノイズだ、と。良く考えずに発言する事なんてしょっちゅうでした(笑)。そこには芸術的機能も無ければ、所謂ビザールと呼ばれるコンテンツもまったく存在していなかったのです。機能もコンテンツもなにも、完結すらしていないマシーンに構造なんてものは無いんですよ。スカスカのテクノイズ(笑)
実に気性の荒い表現方法だったので、例えばライブ当日に集まれるアーティストだけが各自好きな機材を持ち寄り、当然の如く打ち合わせ無しで演奏して、グダグダでも最高の出来でも、ステージ上で音を交換しあって、で、それで終わり。
今だったら「いやぁ実はダダイスティックな方法論を選択していたんですよ」なんて言いくるめる事も可能ですが、その頃は何度も言いますが、まったく何も考えていませんでした。
僕を始め当初のelectronoise groupのメンバーには恐らくその表現/パフォーマンス/演奏に対する爆発的な欲求しか存在していなかったのだと思います。これも今だから言えますが、あの頃の僕らは恐らく大友良英さんが定義する様な「ノイズ」と同じグリッドラインにあったかもしれませんね。いや、同じグリッドと言ってもそれはそれはもちろん遥かデッドエンドの方ですが(笑)
まぁとにかく大友さんのMUSICSの冒頭に出てくる様な、現在の僕があまり好まない類いの「ノイズ」(笑)と同じエリアにあったと思うんです。かなり美化して仕分けするのであれば(笑)
だからといって、ハードコアアティテュードに傾倒していたか?スカムサウンドやハーシュといった類いの音楽を聴いていたか?
それこそ非常階段/インキャパだとかメルツだとか中原先生の暴力温泉芸者にしろ、今だとPainjerkさん、C.C.C.C.長谷川さんのASTRO名義やTNBのデマンド(VOD)作品がとてもかっこよかったgovernment alphaさん(もちろん尊敬してますし、今になってみれば、その中の何組かは同じイベントにて共演させて頂いた事もあります)所謂ジャパノイズなサウンドをコレクトしていたか?まったくそうでも無かったですね。
その頃の僕はナードな(しかもドープな)佐々木 敦チルドレンだったので、基本的には彼の言う事書く事を次々に買っては体内にコンバートしていくオタクと呼ばれる程のサウンドアートマニアでした。草食系男子のサウンドアートフェティッシュというのは、それはかなりストイックで(笑)。大谷さんが言うんじゃダメ、佐々木さんの批評しか読まない(笑)
チェチェンズ[1]とか、クラシックエレクトロニクス、俗に言うアーリーエレクトロニクスですかね、アメリカのムンマ[2]とか、フィラデルフィアの奇才チュードアのレインフォレスト[3]、ルシエのワイヤードローン[4]、スウェーデンのリンドブラッドの月[5]も好きでした、他にはラディグにオリヴェロスといった女性ものも。
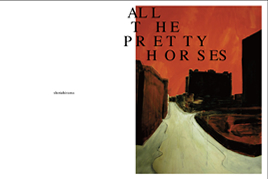
paint by buna
typography + design by Yukitomo Hamasaki(mAtter)
もちろん当時流行の微弱音響、周波数音響も片っ端から聴いてました。ジェフ・ジャーマン、ロペス、ギュンター、後は先日mAtterがキュレーションした恵比寿のgift_labでのPe Lang展にてスピンオフ企画として開催されたARTIST TALKにてインタビュアーを僕が務めさせて頂いたんですけど(スカイプを通して)その時にピーター(Pe Lang)も影響を受けたと言及していたスティーヴ・ロデン[6]も僕は大好きでした。他はやっぱりギターもの、テーブル(オブジエレメンツ)系統ですね。ここもすべてコンプリートしてたかもしれない。因に、このtable of the elementsについては今後mAtterより発売される僕の批評文「ALL THE PRETTY HORSES」にて詳しく言及している一部分がありますので、そこから今回は特別に少しだけ、その一部分をカットアップしました。未公開ですよ。
“しかしあえてニューヨークを中心に活動していたドローンアーティストを選んでみる。その代表として初期Table of the Elements<7インチシリーズの頃>系統の持続疾患者たち。例えばこの男。おしゃれ泥棒集団ソニックユースのノッポ、サーストンムーアに強く影響=ノイズを与えたと言われる墜天使Rhys Chathamだ。もちろん天使と呼ぶには訳がある。1989年のAn Angel Moves Too Fast To Seeという100人ギタリストアンサンブルでのパフォーマンスがその理由であり、彼は先頭で指揮を取り指差すニューヨークの空には世紀を跨ぐまで唸り続けるであろう電子雑音が蛙の様な色合いの反転空間を生む。ひっくり返ったそこから慌て墜ちるエンパイアステイトビルと、リフというルール、リースは100人と100台のギターを音楽的にアップデートさせる、様式はロックミュージックへの懐古主義、未来派の視線、『少しずつゆっくり』は次の変化まで待ちきれず打ち込むヘロインと脈打つロックンロールの興奮を塩とアヴァンギャルドの泡に落とし込んでいく。もしくはその運動、注射器、それが永続的なのだ。この模様はやはりテーブルから2002年にリリースされた『An Angel Moves Too Fast To See (Selected Works 1971-1989)』(カタログナンバーはLa57)という3枚組(3枚目がそれにあたる。1枚目は1971年作品"Two Gongs"が収録、フルクサスジャパニーズYoshimasa Wadaこと和田義正先生とのデュエットである)のボックスで聴き覗く事が可能だ。200ページ近いブックレットにはエッセイと写真があり、こちらも付属している事を確認してから中古屋で買って頂きたい。
そのリース・チャタムの100人ギターアンサンブルで3時間だか5時間の半永久打楽器フェノメノンと化した元SwansのJonathan Kaneもドローンを象徴する、もしくはそのシニフィアンである。2005年発表のFebruary(Table of the ElementsよりカタログナンバーはRa88)は12分、6分、9分、12分の4曲のロックンロールライクなドラムリフが永続的に続く作品。『少しずつゆっくり』のルールに見られる変化はその「打撃の強弱」だけであり、並走するブルージーなベースもギターも『それはまるで入れたり出したり』の二進法的な鬱と超鬱を繰り返す。何も知らなければ何も知らないまま、ブルースだかロックンロールサイケデリアだかな作品としてそれこそ永久的に忘却の彼方、言い換えればそこはサイエンス・フィクションの肥大した外宇宙、夢(あみど)と現実(まど)の誰も知らない隙間へ振り落とされてしまうだろう。試しにitunesでJonathan Kaneと検索してみて欲しい。試聴出来る20秒間に聴こえてくるのは最早一般的音楽だ。なんと社会不適応な音楽であろうか。何度も繰り返すがケーンの『少しずつゆっくり』はその打撃の強弱だけであり、形態こそ一般的概念内に存在する、もしくは既に家畜化してきた姿形である。この普遍的にシンプルなコンセプトをマイナス軸へ還元化するスタイルはニューヨークネオダダイスト達の奥義であり、そこに変化を見つける事が出来るのもまたごく僅かである、という所にTable of the Elementsの粋なはからいを感じる。私が二十歳の時だっただろうか、当時担当者であった某レコード屋その本社にてノイズ担当者に頂いた数多くのサンプルCDの中に紛れ込んでいたこのニューヨークドローンは、私の生涯ドローンベスト10にランクインするであろう作品となった。思い出せば彼は最後にこう言うのだった。「ここで演奏されるすべての楽器はジョナサンが自ら演奏している」即ちベースやギターも、という意味だ。
例えばフルクサスでケージをも喰らう神秘主義でニューヨークの角部屋に自らの体を縛り続けたミスターご隠居人『宇宙・肉体・ラモンテ』ことLa Monte Young率いる持続宗教団体ドリームシンジケート、Theatre of Eternal Musicもドローンの代名詞である。メンバーは機械仕掛けの神ばかりが集っており、エヴァ以降テン年代周辺チルドレンにはあまりにも遠い存在だろうか。ウォーホールを嘲笑う反バナナ分子でご存知初期ヴェルベットアンダーグラウンドのドラマーAngus MacLise(その前任は現代ランドスケープアートの巨匠Walter De Maria、こちらもウォーホールに反体制を取っていただろうと推測出来る)、同じく反バナナ同盟ベーシストにして後にアンビエントへ回収される事となる今やイーノの良き理解者ことJohn Cale、1940年代に生まれ<アメリカンミニマリズム:モダンミニマル>の提唱者である持続再生の狂気、パラドックスルールの癌、バイオリニストTony Conrad。そしてこちらは1930年代生まれの偉大なる現代反復音楽の父Terry Riley、彼もまたラモンテと永久音響を共謀した仲なのだ”
![]()